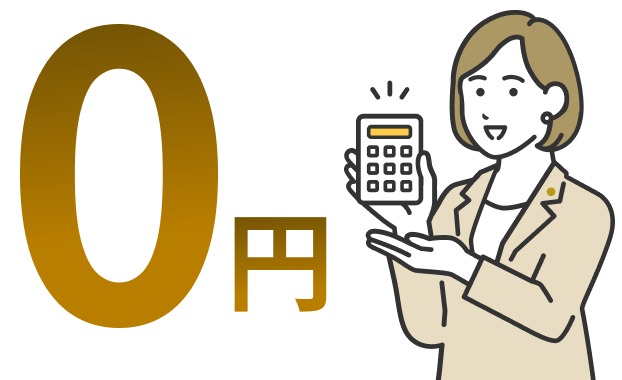遺留分の放棄は生前だけではなく相続開始後も可能! 対応方法を解説
- 相続放棄・限定承認
- 遺留分
- 放棄

平成30年、柏市内では3425名の方が亡くなっています。つまり、これに近い件数の相続も発生していると考えられます。
相続では、相続人同士でさまざまな権利関係が発生します。そのうち、重要なもののひとつとして「遺留分(いりゅうぶん)」がありますが、遺留分を放棄することはできるでしょうか。また、相続放棄とは何が異なるのでしょうか。
本コラムでは、遺留分の基礎知識と遺留分を放棄する方法、さらに遺産分割でトラブルになったときの対処法について、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士が解説します。
1、遺留分の基礎知識
-
(1)遺留分とは?
遺留分とは、民法によって一定の範囲の相続人に最低限保証されている、遺産の取り分のことです。
遺留分の制度が設けられている背景のひとつは、相続人の生活を保障することにあります。たとえば、被相続人の収入や財産を頼りに生活する家族がいるなかで、遺言などにより被相続人が「すべての財産を寄付する」などと指定したとします。これが実現すると、相続人は今後の生活に困窮してしまう可能性があります。このような事態を防ぐために、民法では遺留分の制度を設けることによって、相続人が最低限相続できる遺産の取り分を保証し、ひいては相続人が生活に困らないようにすることを目指しているのです。 -
(2)遺留分の計算方法とは?
民法第1042条第1項では、相続人の遺留分の割合を以下のように定義しています。なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
- 被相続人の父母や祖父母など直系尊属のみが相続人の場合は3分の1
- その他の場合は2分の1
各相続人の具体的な遺留分は、法定相続割合を乗じて計算する必要があります。
たとえば、遺産総額が1000万円で相続人が配偶者と子ども2人であるケースを想定し、遺留分を計算してみましょう。
遺留分総額は、相続人が配偶者と子どものみですので、民法が規定する「その他の場合」に該当します。今回の例では、2分の1が遺留分割合になります。
法定相続割合は、配偶者が2分の1で、子どもはそれぞれ4分の1(2分の1×2分の1)ずつです。
つまり、遺留分は次のようになります。
●配偶者の遺留分
1000万円×1/2×1/2=250万円
●子ども1人あたりの遺留分
1000万円×1/2×1/4=125万円 -
(3)遺留分の対象となる財産とは?
遺留分の対象となる財産は、原則として被相続人の相続発生時の財産すべてです。
もし被相続人の財産に借金などのマイナスの財産がある場合は、それを預貯金や不動産などのプラスの財産から控除した額が遺留分の対象となります。なお、条件付きの権利や存続期間の不確定な権利であっても、家庭裁判所が選任した鑑定人が評価額を付けることによって遺留分の対象となります。
ただし、一部の例外があります。
たとえば、被相続人が契約者および被保険者、相続人を受取人とする生命保険の死亡保険金は受取人の固有財産とされます。そのため、相続財産と扱われず原則として遺留分の財産額に加算されません。
2、遺留分を放棄できるタイミング
相続放棄は、自身が相続人であり、かつ、相続が開始されたことを知ってからでなければ放棄できません。つまり、被相続人が生存しているあいだに相続放棄することはできません。
これに対して遺留分は、民法第1049条第1項の規定により相続が発生する前でも、家庭裁判所の許可を受けた場合にかぎり、放棄することができます。もちろん、相続が発生したあとでも可能です。
なお、被相続人の生前・死後に関係なく相続人の一人が遺留分を放棄したとしても、他の共同相続人の遺留分が増えるわけではありません。
3、遺留分放棄に際しての注意点
-
(1)生前に放棄するときの注意点
民法第1049条第1項では、遺留分の生前放棄について「家庭裁判所の許可を受けたとき」に限定しています。したがって、被相続人の生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所に所定の手続きを行い、許可を得なくてはなりません。
遺留分放棄の許可の申し立ては、申立人の住所地ではなく被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。必要な書類や費用は、以下のとおりです。
- 遺留分放棄の許可の申立書
- 財産目録
- 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
-
(2)死後に放棄するときの注意点
被相続人の死後に遺留分を放棄する場合は、生前の放棄と異なり「私は遺留分を放棄する」という意思表示のみで足り、家庭裁判所への申し立て・許可の取得は不要です。
ただし、遺留分の放棄は、あくまで遺留分のみを放棄するだけに過ぎません。つまり、遺留分を除いた相続財産に対する相続権は残るのです。これは預貯金や不動産のようなプラスの財産に対してだけではなく、借金のようなマイナスの財産についても同様です。
もし、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多かった場合、遺留分を放棄していてもマイナスの財産を相続することになってしまいます。したがって、遺留分だけではなく相続権の一切も放棄したい場合は、原則として相続が発生したことを知ったときから3か月以内に、相続放棄の申述を家庭裁判所に行わなくてはなりません。
相続放棄をする場合は、遺産分割協議(相続財産について、誰が・何を・どの割合で相続するか相続人のあいだで話し合って決めること)の場で、「私は何も相続しない」と書面に残すだけでは法的に不十分です。相続放棄をするためには、家庭裁判所の手続きが不可欠であることに注意してください。
4、遺産分割でトラブルになったときの対処法
遺留分放棄や相続放棄は、相続にまつわるトラブルや、他の相続人と関わらないですむこと、マイナスの財産を相続しないですむ可能性があるというメリットがあります。
一方で、他の相続人から遺留分放棄や相続放棄を求められるケースもあるようです。相続人として財産を相続する権利を行使したい場合は、しっかりとその権利を主張するべきでしょう。
このようなケースでは、相続割合や相続財産などをめぐって遺産分割協議が合意に達しないという事態も想定されます。以下では、遺産分割でトラブルになったときの対処法についてご説明します。
-
(1)遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合、相続人は「遺産分割調停」を家庭裁判所に申し立てることができます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所が選出した調停委員を介した話し合いで、利害関係にある共同相続人どうしが直接の話し合いをしないため、合意に向けて冷静な話し合いが期待できるというメリットがあります。
調停が成立すると、家庭裁判所により「調停調書」が作成されます。この調停調書は、裁判における確定判決と同様に法的拘束力を持ちます。 -
(2)遺産分割審判
遺産分割調停が不調に終わった場合は、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判では、紛争の当事者が書面や証拠資料などを提出しながらそれぞれの主張を行い、裁判官が審理を進めていくことになります。裁判官からの審判が出るまでに1年以上の時間を要する場合もあります。
遺産分割審判の内容が確定すると、相続人がその内容に従わない場合は、強制執行などの手続きを申し立てることが可能になります。ただし、遺産分割審判の結果が出たとしても、2週間以内に即時抗告を行えば、遺産分割審判が確定することはありません。
なお、審理の途中で、裁判官より和解案を示した「和解勧告」が出ることがあります。もし、和解が成立した場合は、家庭裁判所により「和解調書」が作成されます。
5、弁護士に相談するメリット
遺産全般において何らかの不安がある場合、あるいはトラブルが発生することが予想される場合は、できるかぎり早い段階で、弁護士に相談することを検討してください。
弁護士から受けることができるサービスは、法的なアドバイスだけではありません。弁護士は依頼者の法定代理人になることが認められています。つまり、他の相続人との交渉、さらには、遺産分割調停や遺産分割審判にもあなたの代わりに出席することが可能です。
また、弁護士は遺留分放棄や相続放棄の手続きや、家庭裁判所における手続きを代行することもがきます。
トラブルの相手となっている他の相続人と冷静な話し合いが難しいと考えられる場合、あるいは仕事などの関係から家庭裁判所の手続き、遺産分割調停や遺産分割審判への出席が難しい場合は、弁護士に依頼することがおすすめです。
6、まとめ
相続には、思いもよらないトラブルが付き物です。それは遺留分の放棄を迫られたときや遺産分割の場面にかぎりません。
少しでもトラブルの発生が予想されるときは、できるだけ早くその芽を摘むことが何よりも大切です。そのため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 柏オフィスでは、相続全般に関するご相談をお受けしています。相続におけるトラブルの対応実績が豊富な弁護士がしっかりとお話を伺いますので、ぜひお気軽にご相談ください。解決のために、ベストを尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|