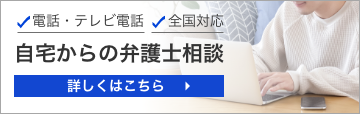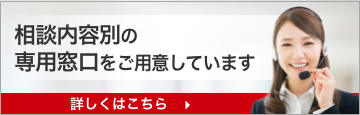裁判の準備書面|効果的な書き方のポイント
- 一般民事
- 準備書面
- 書き方

裁判所が公表している司法統計によると、令和2年に第一審通常訴訟として既済事件となった総数は、12万2749件であり、そのうち原告・被告の双方または一方が弁護士を付けた事件は、11万2860件でした。
多くの方は、裁判となった場合には弁護士を依頼しています。ただ、弁護士を利用することなく自分で裁判手続きを進める方もおられます。自分で裁判手続きを進める場合には、裁判所に提出する書面も、すべて自分で作成しなければなりません。
裁判では、自分の主張をする場合や相手の主張に対して反論をする場合には、「準備書面」という書面を利用して行います。準備書面の書き方については一定のルールがありますので、裁判官に自分の主張を理解してもらうためには、そのルールに従って記載することが大切です。
本コラムでは、準備書面の書き方や効果的な書き方のポイントについて、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスの弁護士が解説します。
1、準備書面とは
まず、裁判における準備書面について、基本的な事項から解説します。
-
(1)民事裁判の流れ
民事裁判は、原告が訴状を裁判所に提出することによってスタートします。
訴状に記載された原告の請求や主張に反論がある被告は、答弁書という書面に主張・反論内容を記載して裁判所に提出します。
第1回口頭弁論期日では、原告が訴状の陳述、被告が答弁書の陳述をして、次回期日が設定されます。陳述といっても、法廷で訴状や答弁書の内容を読み上げるわけではなく、裁判官から「訴状(答弁書)のとおり陳述しますね」と確認を求められるだけです。
そして、次回期日以降に原告や被告にさらに主張したいことがある場合には、準備書面の提出を通じて主張を行うことになります。 -
(2)準備書面の概要
準備書面とは、民事裁判にて、原告または被告が口頭弁論や弁論準備手続きにおいて陳述する内容を記載した書面のことをいいます。
「裁判」というと、テレビドラマでよく見るように、原告と被告が法廷で主張と反論を繰り返す場面を想像する方も多いかもしれません。
しかし、実際の民事裁判では、口頭で主張や反論をやり取りすることはほとんどありません。なんらかの主張がある当事者は、準備書面に主張内容をまとめて、裁判期日までに書面を提出する、ということが通常になります。
裁判官に有利な判断をしてもらうためには、準備書面によって自己の主張を説得的に伝えることが必要になります。
そのため、準備書面の内容は、裁判の結果を左右するほど重要となるのです。
2、準備書面の書式や内容は?
以下では、準備書面の書式や内容について解説します。
-
(1)準備書面の書式
準備書面の書式については、明確な決まりはありません。
しかし、弁護士が代理人として作成する通常の準備書面の書式に従って作成する方が、裁判官としても読みやすくなるのでしょう。
そのため、特にこだわりがないのであれば、通常の書式に従うのがよいでしょう。
① レイアウト
準備書面のレイアウトは、1行あたり37字、1ページあたり26行で作成します。
② 文字の大きさ
文字の大きさは、「12」を使用します。
Wordの標準では、「10.5」と設定されているとことが多いでしょう。
しかし、準備書面はファクスでやり取りすることを前提とする書類です。そのため、文字がつぶれてしまわないように、少し大きめの「12」が用いられているのです。
③ 用紙
準備書面の用紙は、訴状や答弁書と同様に、A4用紙を縦置きにして使用します。
④ 余白等
余白は、上端35㎜、下端27㎜、左側30㎜、右端15~20㎜とし、左端を2カ所でステープラー(ホチキス)止めをします。 -
(2)準備書面の記載事項
準備書面を記載する場合には、以下のような事項を記載するのが一般的です。
① 事件番号・事件名
準備書面の冒頭には、事件番号と事件名を記載します。
事件番号と事件名は、訴状が受理された段階で裁判所の書記官から伝えられます。
例を挙げると、「令和〇年(ワ)第〇〇〇〇号 損害賠償請求事件」といった記載です。
② 当事者の表示
事件番号・事件名の下に、当事者の名前を記載します。
具体的には、以下のように記載されます。原告 ○○○○
被告 ○○○○
③ タイトル
準備書面のタイトルとしては、原告であれば「原告準備書面」、被告であれば「被告準備書面」などと記載します。
単に「準備書面」とだけ記載する場合もありますが、どちらの当事者から提出されたものかを明確にするためにも、原告と被告で区別するのがよいでしょう。
なお、何回か準備書面を提出する場合には、「原告準備書面(1)」「原告準備書面(2)」のように番号を付していくことになります。
④ 裁判所の表示
準備書面を提出する裁判所について、以下のように記載します。○○地方裁判所民事部〇係 御中
⑤ 作成年月日
準備書面を作成した日付を記載します。
⑥ 準備書面作成者の氏名と押印
準備書面を作成した当事者の氏名を記載し、その隣に印鑑を押印します。 -
(3)準備書面の内容
準備書面の内容については、明確なルールはありません。
しかし、裁判官に自分の主張が正しいということを理解してもらうために説得的な内容を記載する必要があります。
また、裁判官にとって読みやすくするために、項目ごとに見出しを付けるなどの工夫も必要となるのです。
3、準備書面を作成する際に注意するポイント
準備書面を作成する場合に注意すべきポイントについて解説します。
-
(1)できる限り短い書面にする
「自分の主張を裁判官に理解してもらいたい」と思うあまり、何十ページにもわたる準備書面を作成される方がおられます。
「必要な事項を記載した結果、準備書面が長くなってしまう」という場合には仕方ありませんが、「たくさん書いた方が裁判官に熱意が伝わる」といった理由で準備書面の枚数を増やすことは、有意義ではありません。
裁判官は、1人で多くの事件を抱えていますので、1件の事件に費やすことができる時間は限られています。そのため、必要性がないにもかかわらず大量の準備書面が提出されると、どうしても流し読みになってしまい、伝えたい事項が伝わらないおそれがあるのです。
したがって、準備書面はできる限り短くまとまった書面にすることが大切です。もっとも、必要な事項がもれることのないよう注意が必要です。 -
(2)証拠との対応関係を明確にする
民事訴訟では、争いのある事実を認定する場合には、証拠に基づいて行われます。
そのため、準備書面の提出とあわせて、自分の主張を裏付ける証拠がある場合には、証拠の提出も行う必要があります。
準備書面を読んだ裁判官に、「どの主張が、どの証拠と関係しているのか」と理解してもらえるようにするため、準備書面では、証拠と主張の対応関係を明確にするようにしましょう。
たとえば、売買契約を裏付ける証拠として売買契約書(甲第1号証)を提出する場合には、準備書面に「XとYは、令和〇年〇月〇日、○○を目的物とする売買契約を締結した(甲1)」などと記載する、ということが必要です。 -
(3)時系列に沿って記載する
争いごとは、時間の経過に沿って進行していきます。
そのため、「どのような経緯で争いが生じたのか」「争いの背景にはどのような事情があるのかを裁判官に理解してもらう」ということが大切です。
そのためには、事実関係を記載する際に時系列に沿って記載する必要があります。
一方で、時系列をバラバラに記載した準備書面では、裁判官にとって読みづらいため、重要な事実を見落とされてしまう可能性があるでしょう。 -
(4)事実と評価は分けて記載する
裁判では、ある事実を認定して、その事実を法律に当てはめて評価することにより、一定の結論が出されます。
そのため、当事者は具体的な事実を主張することになります。
したがって、事実を端的に記載した方が、裁判官に伝わりやすい準備書面となるでしょう。
また、当事者の主観的な評価を書く際にも、事実と評価を分けて記載することが大切になります。 -
(5)同じ内容を繰り返さない
民事裁判では、当事者からの主張と反論を繰り返すことによって争点を整理していくことになります。
争点整理のために複数回の期日が行われるケースでは、準備書面のやり取りも複数回行われることになります。
準備書類を複数回提出する際には、つい、同じ内容を繰り返して記載してしまう場合があります。しかし、特に強調しておきたい部分以外については、同じ内容の繰り返しは避けるようにしましょう。主張したい事実を繰り返して記載したとしても事実関係の存否は証拠によって判断されます。
4、準備書面の提出方法・期限
以下では、準備書面の提出方法と提出期限について説明します。
-
(1)準備書面の提出方法
準備書面は、裁判所提出用の正本と相手方提出用の副本を作成して、以下のいずれかの方法によって提出します。
- 裁判所に正本と副本を提出して、副本を裁判所から相手方に送付する方法
- 裁判所に正本を提出して、副本を相手方に送付する方法
- ファクスを利用する方法
裁判手続きにおいて書面を提出する方法は、郵送でないといけない場合とファクスを利用して提出することができる方法があります。準備書面の提出は、ファクスの利用が認められています。
弁護士が相手方の代理人となっている場合には、裁判所に提出した準備書面は、相手方の法律事務所にもファクスを送るようにしましょう。 -
(2)準備書面の提出期限
準備書面は、裁判期日において裁判官から指定された期限までに提出する必要があります。一般的には、裁判期日の1週間前が、準備書面の提出期限と定められます。
提出期限までに準備書面を提出することが望ましいですが、提出期限を過ぎたからといって、そのあとは準備書面の提出が一切認められない、ということはありません。
裁判期日までに準備書面の提出が間に合わないような場合には、裁判期日で事情を説明して、新たに提出期限を設定してもらうとよいでしょう。
5、まとめ
民事裁判を、弁護士を付けずに本人のみで進めていく場合には、本人が準備書面を作成する必要があります。
準備書面によって説得的に裁判官に事実を伝えることができなければ、自己に有利に裁判を進めたり、有利な判決を得ることも困難になります。
「裁判の準備は弁護士に依頼せずに進める」という方であっても、準備書面の作成に少しでも不安がある場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
裁判に関するお悩みは、ベリーベスト法律事務所 柏オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています